昭和36年(1961年)生まれの皆さん!
「あ、また自分だけ仲間はずれだ…」
そう感じたことはありませんか?
もしかしたら、人生の節目節目で、制度の変更や区切りの影響を受け、「適用外」となる場面に遭遇してきたかもしれません。
今回のテーマである「特別支給の老齢厚生年金」も、その一つかもしれません。
知っておきたい「特別支給の老齢厚生年金」
老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取れる年金ですが、以前は60歳から支給されていました。しかし、少子高齢化が進む中で、年金制度を長期的に維持するために、支給開始年齢が段階的に引き上げられることになりました。
この移行措置として設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。これは、生年月日や性別によって、60歳から65歳になるまでの間に、本来の老齢厚生年金の一部または全部を受け取ることができる制度でした。
しかし、この制度には明確な線引きがあり、昭和36年4月2日以降に生まれた男性、そして昭和41年4月2日以降に生まれた女性は、この特別支給の対象外となっています。つまり、昭和36年6月生まれのあなたは、まさにこの「適用外」に該当するのです。
なぜ昭和36年生まれは「適用外」が多いのか?
特別支給の年金制度だけでなく、他の制度においても「昭和36年生まれは適用外」と感じることがあるかもしれません。これは、社会の制度や法律が制定・改正される際に、特定の年次を基準として区切りが設けられることが多いためです。
例えば、過去の税制改正や保険制度の変更など、多くの制度変更が年度ごとに行われるため、4月1日を基準とした年齢区分が用いられることが一般的です。そのため、年度の途中に生まれた昭和36年生まれの方は、前後の生まれの方々と比べて、制度の適用範囲から外れてしまうケースが生じやすいと考えられます。
もちろん、これは意図的に特定の世代を不利に扱おうとしたものではなく、制度設計上の都合によるものがほとんどです。しかし、当事者からすれば、「また自分たちの世代だけ…」という思いを抱いてしまうのも無理はありません。
「適用外」という名の運命を受け入れる?
制度の狭間に置かれることで、不公平感や諦めを感じてしまうこともあるかもしれません。「自分たちはいつもこうなんだ」と、半ば運命のように受け止めてしまうこともあるでしょう。
しかし、本当にそうでしょうか?
もちろん、過去の制度変更をなかったことにしたり、自分の生年月日を変えたりすることはできません。しかし、「適用外」という状況をただ嘆くだけでなく、それをバネにして、他の道を探ることはできるはずです。
例えば、特別支給の年金が受け取れない分、65歳からの年金受給に向けて、より積極的に資産形成に取り組むという選択肢もあります。また、健康寿命を意識して、長く働くことができるように健康管理に力を入れることも重要です。
世代間の連帯と制度への関心
私たち一人ひとりの力は小さいかもしれませんが、同じような思いを抱える世代が集まり、声を上げることで、社会に変化をもたらすことができるかもしれません。
年金制度をはじめ、社会保障制度は、私たち国民一人ひとりの生活に深く関わるものです。制度の内容に関心を持ち、必要であれば意見を発信していくことも、私たちが社会の一員としてできることではないでしょうか。
『適用外』を乗り越えて
本記事は、特定の制度に対する批判や不満を煽ることを目的としたものではありません。制度の仕組みを理解し、自身の状況を踏まえた上で、より良い選択をするための情報提供を目的としています。最新の情報は、必ず関連省庁や専門機関にご確認ください。

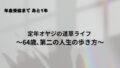


コメント